※お題募集記事の為本文は
一定数コメントが集まった後追加という感じになってます。
【鉄血のオルフェンズ】ガンダムフレームってみんな腰のフレーム丸出しなの危なくない?
ワンピースでエースが死んだときの当時の反応wwwwwww
【悲報】ゼルダ新作の通称「コロ虐」、限界突破してしまうwwwwww
【謎】「ポケモンBW2ってなんで3DSで出さなかったの?」→こういう理由だった
鬼頭明里さん、めざましテレビでママ化する
【悲報】モンハンワイ、操虫棍が使えなくて咽び泣く
おもっていたことを全部>>1で片づけられてしまったw
逆に変えない部分だけど
作品自体はどんなに過激で野心的なストーリーでも
主人公はブレない善の心を持ってる
子供向け、として放送されてるから当然なんだけど
ライダーバトルの中で善の心を曲げない事が如何に難しいか
大人になってから見ると、それが凄く分かって真司を本当に尊敬する
だから今でも愛されてる作品なんだろうなあ
まあこれは龍騎だよね
何作もやった後の変化球ではなく、初期の3作目でやったのも凄い
ゼロとベリアルを生み出したのはデカイ
そんな事が一つ残らずどうでも良くなるくらいキャラが濃過ぎたドンブラザーズ
キン肉マン等を参考に敵キャラや味方キャラにも個性を出し商品を増やすことで武器などのアイテムを売る必要がなくなった結果メタルダーが終始素手ベースの戦いをする点は良い路線変更だったように思える
・M78星雲以外のウルトラマンを本格的にテレビシリーズに登場させる
・光と闇の対立の構図
・ウルトラマンで初のタイプチェンジ
・アイドルを主演に起用
枚挙に暇がない

出典:https://m-78.jp/character/tiga/
光と闇の対立に関しては、設定だけとはいえ光の国vsエンペラ星人軍団はタロウ時代からありましたな。
個人的にはその後
「なぁ、もっかいゴジラ悪役として出したいんだけどどうすればええかな?」
「ゴジラもう一体出したらいいんじゃね?」
「それだ!!」
で生まれたメカゴジラも中々凄いと思う
龍騎はそれまでの仮面ライダーに無かったフォーマットやストーリーを躊躇いなく盛り込んだ革命作
555はクウガ~龍騎まで次年度の放送枠確保を優先してたのに対し、この年で本格的に「平成仮面ライダー」の枠を決定づける覚悟で作った作品
電王はそれまでのいわば平成1期のレシピを捨てて、全く新しいレシピを考案した作品
OOOは一見すると典型的な平成2期に見えてどっちにも微妙に当てはまらない作風を持った特異点(意訳:小林靖子パネェ!)
らしい
響鬼まではキャラや空気感がドラマって感じだけど、カブトからアニメっぽいやや大袈裟なキャラ付けや演出が増えた印象
そして電王でイケるやん!ってなって現在の作風に至る
本編終了後の展開も電王以前と電王以後で違うよね
当時はどんだけ映画出すの!って思ったけど
やっぱ好きな作品がずっと何かしらで続くのは嬉しい
響鬼までというか、響鬼のあたりで仮面ライダーシリーズが固定化というか、毎年これで最後カモっていう状況だったのも大きそう。
番組初期まではたしかまだロボットのデザインだかなんだかがまだ完全に決定してなかったから
番組最初の数話分は敵味方双方ロボットの設計図めぐる争奪戦多かったのも斬新だったな
劇中まだ未完成で建造中のバトルフィーバーロボのシルエットに当時ワクテカした記憶
視聴率が低迷した時代に作られて復権するきっかけになったという作品
ここら辺でストーリーについての方向性が定まって来たように思える
あとは「ロボット」の方向性を決めていしまったのがガオレンジャー
正直賛否両方あるスタイルだと思うけどプレイバリューと売り上げを両立させるスタイルを作ったのがコレかな、と
その後休止明けとなった戦隊シリーズにも持ち込まれましたし。
・六人目の戦士のレギュラー化
・RPG風の試練イベント
・敵組織の全滅EDではなく、封印or次世代に再戦(和解?)などのビターエンド
今でも文芸面で高評価される所以
これらの特徴は、ジュウレン~オーレンまでの杉村升脚本の特色
初代パワレンでもあるから、新世代の1発目という印象が本当に強い。
パワレン化自体はタイミングの問題ではあるけど。
戦隊ヒーローが防衛組織に属していたりスーツや武器をその組織が開発していたそれまでのスーパー戦隊シリーズから明らかにフォーマットを根本的に変えた作品だったよね
若い世代には判りづらいかもしれないけれど、バイオマンは戦隊ものの「中興の祖」と言っている人が多い
ヒロインが二人で心配されていたけれど、ふたを開けたらスポンサーから5人全員女性の戦隊をオーダーされたりとか、まさに転機になっている
鈴木P、曽田脚本、出渕デザインの時代
戦隊が今に続くアニメテイストの実写作品に変化した時期だと思う。
「全てを破壊し、全てを繋げ!」は東映の宣言だった
ディケイドが現れたお陰で新旧作のクロスオーバーが可能になる
次第にディケイド関係なくライダー達は作品を跨ぎ出し
彼はその役割を(一旦)終えた
クロスオーバー作品の中には
首を傾げる様なストーリーの作品があるのも事実
「このライダーはこんな事言わない、やらない」ってぶち壊されたキャラもいたが
それでも過去のライダー達が現れ、戦う姿はやはり良い
クロスオーバー自体はそれより前の「クライマックス刑事」で既に実現済みですぞ(仮面ライダーキバと電王のみだったけど、それでも「複数作品ヒーローの共闘を平成ライダーシリーズでもやってくれた」事は嬉しかったなあ)
単発のゲスト子役がなくなって縦軸のストーリーが強化された感がある
それだけじゃなく、ギンガマンから継承されてる要素もかなりある
・第⚪︎話ではなく第⚪︎章「××の△△」という個性的なサブタイ
・ホルスターに拳銃ではなく剣1本
・秘密基地代わりの仮住まい
・1つのガジェット「アース」に世界観や物語を象徴させる
・必要最小限のキャラだけで話を進めるミニマルな演出
・レッドが正規メンバーではなくイレギュラー
ガオ以降で定着する戦隊のスタンダードの源流って感じ
確かにギンガマンで高寺プロデューサーの名前を覚えた
パワーアップするようになっていったのはガオレンジャーからか。
足をちょっと開くのもここからだったな
・改めて捉え直したウルトラマンの神秘性
・改めて捉え直したウルトラマンと人間のファーストコンタクト
・地球環境に関する問いかけ
・ゴーデスのようなヴィラン枠による縦軸の展開
・ナックルシューター、フィンガービームのような牽制技の多用
・光の剣の使用
他にも色々あるだろうけど、どの要素もティガ以降に大きな影響を与えている。
マグナムシュートのような球体の光線技の影響も大きいと思う
ウルトラ兄弟という言葉は「帰ってきたウルトラマン」の最終回で既にバット星人が口にしていたよ
前作の新マンで「過去作のヒーローを客演させる」手法が導入されたことも大きい。
その過去作のヒーローが客演し、パワーアップアイテムを授けるのも追加で
フォームチェンジはティガをはじめとしたウルトラシリーズにも影響を与えたと思う。
ここで宇宙刑事第4作が製作され、以後も続いていればメタルヒーローシリーズの多様な展開はなかったかもしれない。
それでも宇宙ヒーロー路線は続いていったが
スーパー戦隊さながらの巨大戦を展開したことで
宇宙刑事シリーズとの差別化を図ったな
振り返ってみりゃヤプール、スフィア、アクセラーって似たようなのはいるんですけど
後、1番手の武器に追加銃を加えての合体最強銃
ライダーもフォーマットって意味では平成2期の開始が大きいと思う 冬映画の開始だったり夏映画の意味合いなんかもガラッと変わったしね
X1マスク
いやそれ以前のマグネ戦士って何だったんだろう?
おそらくマグマ戦士は黒崎輝さんのジャスピオン主演のカメラテスト
X1マスクは、脚本井上敏樹さんの変化球
仮面ライダー扱いされない女性の変身戦士(ストロンガー)
ライダーには含まれないがアギトと一時同じ姿になった女性(アギト)
劇場版限定の女性ライダー(龍騎)
イレギュラーな形で本編で変身(ファイズ)
量産型だがTV本編で正規の変身者に(ウィザード)
レギュラー化(鎧武)
メインヒロインが変身(エグゼイド)
初期から登場(ゼロワン)
商品展開前提のキャラじゃないのに登場させたんだから仕方がないけれど
真由メイジの量産型扱いがもったいなかったなあ。
本編中であんだけ扱いのよかった女性ライダーはまだ少ないでしょ。
ロボの販促もそうだけど、仮面ライダーアギトがクウガを踏襲して高学年以上を狙うなら、戦隊は未就学児から低学年を狙う、ってコンセプトがハッキリしていてストーリーが分かりやすいし子供を飽きさせない工夫に満ちていて、一つのスタンダードは確立したんじゃないかなあ。
パワーアニマルをCGにしたことで表現の幅が広がり生物らしさがでたと思う
フラッシュマンはフラッシュキングが大破して、その間、巨大化した敵に苦戦し続けて、ようやく2号ロボ登場の流れが素晴らしかった
ベルトとは別に、小物を単品で大量に売るようになった
射幸心を刺激されて、当時は転売ヤミーが大量発生した
アクションが大野剣友会からJACに変わって、トランポリン多用したアクションになったな。BLACKやRXはとにかくジャンプして攻撃してたイメージが強い。
大野剣友会、JAC(JAE)どっちも好きだけど、また剣友会っぽいアクションのヒーローも見てみたいな。
特にブラックコンドルこと結城剴
変身後も名前呼びなのもジェットマンからだね
実はファイブマンの中盤以降から
最初は色で呼んでいたけど途中から名前で呼ぶようになる
ここから仮面ライダーは本流(昭和、平成、令和で区切られるテレビシリーズ)とは別のVシネ(真仮面ライダー)、映画のみ(ZO、J、THEシリーズ)、配信(アマゾンズ、BLACSUN)など主に大人をターゲットとした亜流へのラインがスタートした
石ノ森先生が生前最後に関わった仕事でもあるんだよね
M78星雲のウルトラマンに昭和怪獣の復活
昭和怪獣の復活は今でも続いてるしマックスでやった意義は大きい
ティガ以来、昭和とは違う独自路線を走ってきた平成ウルトラだったが、ネクサスの商業的失敗が昭和ウルトラへの原点回帰に繋がった
もし成功していたら、その後のマックスメビウスも無く、ゼロも生まれなかった?
映画の歴史そのものを変えた
ジャグラスジャグラーという等身大でストーリー上終始暗躍するヴィランを生み出したオーブ
この二つは転換点だと思う
これの成功がなければMCUは始まらなかったかもしれない
仮面ライダー扱いするかどうかは今も意見が分かれるが(自分はライダーに含める派)、「オリジナルデザインのヒーローと同系統の外観をした悪のヒーロー」として画期的だった。
うーん…
すでにショッカーライダーという「悪のライダー」がいたじゃないか!と思ったが、あれはどっちかつーと偽ライダーの系譜になるのか…?
オニタイジンは「戦隊ロボの合体すると知らないおじさんの顔が出てくる問題」が面白かったので今後どうなるか密かに楽しみにしてる自分がいる
クウガはシリアス路線の開拓であると同時に昭和シリーズへの根強い原点回帰でもあった
アギトはシリアス路線を踏襲しつつ複数ライダーの群像劇を展開し、等身大の人間が生きている物語を描いた
龍騎はその群像劇を発展させ、仮面ライダーの設定を大幅にアレンジしつつも正義とは何?というテーマを鮮烈に問いかけた
555は勧善懲悪を超えて人と怪人を隔てる壁で衝突する群像劇になり、もはや問いかけですらなく登場人物だけが生きて決断する話になっていった
そしていずれの作品も孤独な戦士の悲哀、創造主への叛逆、力の使い道は正義の心を持つか否か、仮面ライダーも元々は怪人と同質の存在であるという形でそれぞれ石ノ森章太郎リスペクトを図っている
変身ポーズ自体にちゃんと意味があったり(個人的に最新鋭の科学技術を古流武術の構えで起動するというのが浪漫あって好き)
少林寺拳法主体で戦うスタイルだったり
ファイブハンド換装ギミックは今のシリーズに通じるものも多いイメージ
セブンガーを始め巨大ロボットを本格的に防衛チームの戦力に組み込んだのは大きいと思う
その後はナースデッセイ号、テラフェイザー、アースガロンと路線が続いている
一応ダイナでゲスト扱いだけどマウンテンカリバー5号がいるけど
セブンガー復活はともかくキングジョーが味方ロボットになって出ます!って発表された時は我が目を疑ったわ
フラグだろ?とか思ったもん(小声)
ウインダムとかは メビウスや銀河伝説で把握済みだけど
レオのゲスト怪獣(…でいいのか?)だったセブンガーが
まさか防衛チームの主力部隊になるなんて、夢にも思わなかったよ。そういう面でもZはやっぱ面白い
今やある意味名前自体が知られたジャンルになった牙狼シリーズ
変な話は特にパチンコ関連でも重要なジャンルに
今後の円谷のアニメがどう展開していくのかで後に解釈されるんだろうな
物語途中いわゆる2号機ロボが登場したのはジャンボーグAが元祖だと思う
空を飛べるのと空を飛ばない2体編成っていう点でもな
実際この前後からが今でも十分見れるCGという印象がある
ただそれまで戦隊メカの全合体が好きだった派だから
スーパーガオキング等が出来なくなったのは 個人的に少し残念だな?と思った…。😅
今はそういう展開あんまりないのかな?あいまいな当時の記憶だと戦隊シリーズってある時期から物語途中でほぼ必ず敵の内部での政権交代や内乱が起こるのがお約束になってた記憶があるんだけど…何の番組が最初だったかな?
でも記憶違いだったらすみません
敵組織の内紛展開が後半のドラマの主軸になったのは4作目のデンジマンからかな
むしろ初期の戦隊は主役側は模範的なヒーロー然とした描き方しか許されなかった分
敵側の愛憎劇やら下克上やらで連続したストーリーを作ることが多かった
あいつからクウガ以降の仮面ライダーの共演が始まったし、アイテムをストーリーに取り組んだ作風がみられる様になったからね。
それまでのイケメン俳優で女子人気を高めていた上で人気声優を起用して更にファン層を広げた
以降のライダー作品はレギュラー出演に人気声優が常駐したケースが多い
クウガはファーストガンダムという説明が腑に落ちる
“世界や組織の謎が割と早く明かされる””今迄は最終盤の見せ場だった
世界の崩壊やラスボスクラスとの対決が前倒しで描かれる””だが更にその先がある”
“物語が縦軸に振り切っていて怒涛の展開が続く”という作風のはしりとなった
鎧武も大きな転換を迎えた作品の一つだと思う。
最近は更に縦軸で進めつつ2話完結も織り交ぜたり(セイバー等)
章毎に世界観や登場人物を一新するという形に発展(ギーツ)したりして中々面白い。
レッド以外がリーダーのカクレンジャー
1つの番組に2つの戦隊を出したハリケンジャー
追加戦士がほぼずっと敵対&敵組織の大将のアバレンジャー
等身大戦とロボ戦を同時進行したゴーバスターズ
ここから劇中に登場するヒーローの手持ちアイテムが充実しはじめたし、後の平成仮面ライダーにも受け継がれていると思う。
女性二人になったバイオマンあたりかなあ
いわゆる、「戦隊もの」と言われて思い浮かぶ
ベタというか王道なイメージはほぼゴーグルファイブだね
(崖の上で色付き爆発など)
みんなどこか不謹慎なのに好き
以降レンジャーを崩して使うようになりジャーだけ付ける戦隊も出るようになった
但し元を辿ると怪奇大作戦のSRIから頂戴しているとは思うけど
特撮、スーパー戦隊ではグレートファイブが初だったっけな
良くも悪くもテンプレートな話が多かった戦隊シリーズで
ロボ戦や個々の変身を時々カットしてお話の密度を上げたドンブラザーズは真面目に変換点だと思う。
次作のキングオージャーもロボや怪人が出てこない回があったりとテンプレートにはまりすぎないよう意識していると思う。
1作目だと謎の人食い宇宙人だったのが、この2作目で狩猟民族という設定が生まれて、キャラと世界が広がった感がある
あと宇宙船の中にさりげなくエイリアン(ゼノモーフ)の頭が飾ってあったところから、AVPシリーズに繋がった点も外せない
ゴーカイジャーに受け継がれ定番に
デザインもそれまでのフォーマットぶっ飛ばした物だけど
設定も「仮面ライダーのスーツは怪人用の強化スーツ」って滅茶苦茶な奴になってる
そのせいで、モブ怪人がライダーに変身するなんてとんでもない回もあった
極めつけは
主人公が怪人に変身して、敵の変身した仮面ライダーと戦う
という衝撃
バイクにすら乗らずに駆けつけるようになったのって何時の頃からだったっけ...
ライダーはエグゼイド、スーパー戦隊はボウケンジャーからだな
ライダーのほうはバイクではないけどタイムマジーンは
タイムトラベルモノゆえに出番は多かったが
リバイスでは自転車で駆けつけるシーンは
お世辞にもかっこいいとは言えないよな
メタルヒーローの幅を広げたな
バイクや車以外の等身大マシンも増えていった
元々ウケる要素としては十分なんだけど
まさか味方ロボット枠が毎作恒例になるほど当たるとはさすがに予想外だったわ
変身用携帯電話を持たせたことも大きい
組み合わせの共通点を見つける楽しさもある

Twitterでも配信しているのでフォローしていただけると嬉しいです。
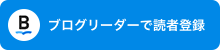

こちらのアカウントのフォロー・サイトのチェックもして頂けると嬉しいです。
https://hero-times.com/





白倉P曰く、そして個人的にもそう思うけど
仮面ライダー龍騎
多人数ライダーおよびライダーバトルの本格化が注目されがちだけど勧善懲悪への懐疑的なストーリーが一番大きいかな