
それと戦う巨大戦の敵が等身大戦の途中に援軍として送り込まれるというスタイルも今となってあえてお約束を外した展開として定期的に使われるけど、当時の制作に携わったスタッフさん達からすると初めての巨大な戦隊ロボのため前例がほとんど無いだけに色々手探りしながら作っていったんだろうなと苦労が伺えた
※お題募集記事の為本文は
一定数コメントが集まった後追加という感じになってます。
という経緯で生まれたらしい、ゴーグルブラック。
バトルケニア・デンジブルーで実績のある大葉健二さんの同期である春田さんを抜擢。
結果、二年連続ブラックが加わり、両方春田さんが演じるというまさにレジェンド級の活躍

敵役なら、マッドギャラン・摩天郎と黒に縁のある春田さん
怪奇ドラマのままだったら、たぶんここまでヒットしてシリーズ化してなかったよね。
牙狼みたいになる可能性はある。(遊戯メーカーとの提携ありきだけど)あの時代に果たしてそれが出来たかというと疑問符がつくから何とも言えない。
もし藤岡さんのことがないまま路線変更したら
おそらく本郷猛がある回から
唐突に一文字的な明るいキャラになっていただろうから
まさに「怪我の功名」だったと思う
序盤なんかライダーキックが決め技でもなく技の呼称すらしてなかったからね。
あと怪人が爆発しないとかとにかくアクションよりも怪奇性がメインだった
ダブラーをギャバンが倒しモンスターは巨大化してドルと一騎打ちの構成が、後にダブルモンスターに集約されて、シリーズでお馴染みレーザーブレードの一閃でギャバン単体で事件解決へと至る構成へと変遷した。
「レーザーブレード!」のかけ声でテーマ曲がかかる定番構成も、その辺りで確立した感じよね。
まぁ、蒸着していない烈がクラッシャー達と一緒に勢いでぶっ飛ばしているのは、モンスターもダブルモンスターも変わらなかった気がするのだけどw
ダブラーじゃなくてダブルマンね。
ダブラーはダブルモンスターの略称。
例の処刑BGMもそのために用意した曲じゃなくて、たまたまそのシーンに当てたらピッタリだったから定着したってね
元々はマクーのテーマ曲「襲撃」だしな。
敵用のテーマにしては格好良い曲な気はするが。

そもそも着ぐるみだってストップモーションで撮影している時間がないから苦肉の策で採用したんだしな。
もし撮影時間が潤沢にあったら日本の映画史は変わっていたかもしれない。
だけど、新しい企画が決まらなくて、前に没になった企画であるロボコンを始めたら、大ヒット!!
その後、平成、令和にリメイク化&映画化♪
仮面ライダーの初期では怪人(や戦闘員)が斃されたときに
爆発ではなく泡となって消えていく表現がされたこともあったっけなぁ
最初に爆死を表現した敵は爆弾関係の作戦をやってて
必殺技食らい死亡と同時に爆弾と共に爆散
当時これは数ある怪人の死亡パターンの一つのつもりだったけど
大好評だった為積極的に取入れるようになった
だっけ?
他には紐で表現とかね
ベレー帽に顔ペイント&全身タイツ➡️目出し帽&全身タイツですね!
本郷猛が戦闘員に変装する為に、目を隠すマスクから始まり、顔も隠すように変わっていった
第二部では敵のまんじ党まで白・黒・青・赤・黄・茶・緑と色違いのスーツ着てたな
お前らが戦隊かよとw
映像作りの創意工夫ってワクワクするよね。
なので、サメ視点の映像で獲物に近づく描写とBGMで演出したとか。
ゴジラの鳴き声は、コントラバスの弦に松ヤニを塗り、革手袋で擦った音を逆再生したもの。
ゴジラの鳴き声に関しては、既存の動物の声を加工したり様々な楽器やSEを試したけどしっくり来なくて、どうするかと途方に暮れていたらとあるベテランの音響技師さんが「これ使えよ」と持ってきた音がまさにあのゴジラの声で、どうやって録ったのかと聞くと「コントラバスの弦に云々」という件の説明をされたと。しかし後に言われた通りにやってもゴジラの声を再現できず、本当にそうやって録ったのかはいまだに謎なんだという話を聞いたことがある。だからゴジラの声ってずっとその最初のテープのものから使われているらしい
先輩ヒーローの客演
過去の人気怪獣怪人再登場
コメディ路線への変更
美人or美少女の仲間or敵幹部を導入。
御題が「シリーズ作品」だから当然だけど、上2つが使えたのはライダーとウルトラだけだよな・・・。
戦隊でさえ作品世界が違うから使えなかったわけだし。
レッドマン「……」
着ぐるみが高下駄過ぎてマトモにアクションが出来なかったとか
戦闘が基本飛び道具(ソードビッカー)一発で終わるのはそのため
終盤はスーツの劣化・盗難のせいで新規映像が撮れず戦闘シーンがバンクのみになった
ジャイアントロボと大鉄人17は違うんだ!
というか、先代が負けた敵を倒せる現行ヒーロー強い!
って持ち上げる時代だったんだろうな
ライダーの方も設定的な敵の強さはインフレ気味に増していってたような感じだった気がする(クウガ⇒アギトでもあった流れ)
2話の時点でアギト作中は2001年だが、未確認生命体事件は2年前(1999年)の出来事であると語られてクウガとは繋がってないとこは明示されてたでしょ。
混乱した視聴者のために公式ページでクウガとは繋がってない世界と解説されてたし。
そういう微妙な関連性を示唆する要素も無くなったということでは。
科学特捜隊ベムラー➡️科学特捜隊レッドマン➡️ウルトラマン…ですね♪
初期戦隊主人公二人のアカレンジャー、スペードエース(あとズバットやアニメ版月光仮面)の武器が鞭なのは、何か流行りの元があったんだろうか。西部劇の投げ縄の影響があるのかと勝手に推測してるけど、ご存じの方がいらしたらお教えいただけると幸い。推測でももちろん聞いてみたいところ。
スペードアーツは「弓の弦を外して鞭にも使っている」印象だった。名前の「アーツ」もアーチェリーのことだろうし。劇中では「唸って躍る核の鞭」と言っていたが。
ハミィも瀬奈お嬢様も好評だったから緑が女性でもいいというのは完全に確立したと思うが。
OPをBGMにしたり、EDをBGMにしたり、オリジナルの曲にしてみたり、無音だったり。
最終的に、OP`に行きついたゴレンジャーと、EDに行きついたデンジマンが印象的。
ゴレンジャーの第1話と第2話を見ると、戦闘シーンのBGMが主題歌でいくのかEDでいくのか模索している感じだった
ダンスがモチーフってのが、子供に全く受けなかったのか速攻で消滅する。一桁話のアクションシーンでは確かにダンスっぽい動きで戦っている。正直ヘンテコなだけで格好良くはない。
すぐに無くなったにも関わらず、作品紹介では「ダンスがモチーフ」「ダンスで戦う」などと言われることがままあるので、見たことのない人たちからはかなり誤解されている気がする。
合体攻撃のペンタフォースの前に謎の人文字でBFと形作ってから攻撃する謎演出があるのだが、これもクッソ格好悪くて受けなかったと見え、すぐに無くなった。試行錯誤は仕方ないんだけど、子供がごっこ遊び出来ないものを何故入れるのかw
人文字については、見たことがないと「何わけわかんねーこと言ってるんだこいつ」だろうけど、他に説明のしようがないんだ……!
BFの人文字は日本的なヒーロー像から敢えて突き放している味わい深さがある
そのかわり、戦隊シリーズ初の戦隊ロボット、バトルフィーバーロボは
歴代戦隊ロボの人気ランキングでもいまだにほぼ殿堂入りレベルのカッコよさ!
生物感を出すために採用されたマジョーラカラーは後の平成ライダーにもアレンジして受け継がれた
そんなんを繰り返して挑戦的で人気のあるものが出来ていくと思うね
ジャッカー電撃隊や仮面ライダーXは正直イマイチな面のある作品だけど後の成功に繋がる挑戦をしていると思う
あれは最初の暗黒魔戒騎士編の時はシリーズ化するつもりが無かったから鋼牙を終了時に最強無敵の完璧な主人公として成長させて完結してるので鋼牙主人公のままでは続けようが無いため、交代は必然。
MAKAISENKIにしろ、蒼哭ノ魔竜にしろ、鋼牙をパワーダウンさせるという苦肉の策で作ってるし。
そう言われると交代よりもMAKAISENKIと蒼哭ノ魔竜での鋼牙の弱体化の理由付けの方に試行錯誤感を感じるな
生前の大野剣友会の創始者の方が俺が発案したとインタビューで語られてましたね
最初は光線撃たせるかとか話してたけど、バッタの改造人間だから飛ばして蹴らせればいいと。投資額としてもトランポリンさえ用意したらそれだけでやれるだろう?とも。
相手が人間ならトドメを躊躇する設定は児童にウケず、また人間であるヨロイ軍団以上に人間的なロボットやモンスターの登場で有耶無耶に…
当初はギリギリまで変身しなかったけど、ビッグワンが登場した辺りから冒頭既に変身した姿で戦う様になったな
生身バトルして「よし、変身カプセルに入るぞ!」いったん引き上げる。
で、改めて怪人に相対したところで
「貴様たちが噂の!」
ってやるのは何とも締まらない。正体知られてないなら成り立つかもしれないが、知られた後でも平気でやるからなあ。
サイボーグ設定もあまり生かせてないと感じた。血は流すし洞窟で窒息するし毒ガスも効くし。
ってんで二話からマスクに変更されたマグマ大使
顔出しはパイロット版だけじゃ無かった?
侵略者たる敵宇宙人の名前をどーんとタイトルに持ってきた画期的な試みだったが、
流石に受けが悪いと判断され変更の憂き目に。
内容も当初扱っていた公害題材がスポンサーの反感を買ったため路線変更を余儀なくされたとか。
複数の決め技、等身大怪人数体等々、定着しなかったのも多々ある中、
女性メンバー二人という定石を産んだ功績は大きいという思う
さらにその女性メンバーの内1人は、もう皆さんご存知のあの事情で素顔が全く出ないまま突然戦死と言う悲劇も…
最初は外部からカメラマンがくると聞いてたのに、いきなり1話からお願いされた いのくまさんを筆頭に苦労の連続。『見えすぎる欠点』をどうするか等。
アテレコが無くなったのも大変だったみたいです
撮影中に入ってしまう音に対する対処の話を聞くと手間が増えた
意外と話題に上がらないけど、ロボには基本3人しか乗らなかった
医師ヒーローの先駆けだったり、チャレンジ精神いっぱいだったね。
小津家の女性陣もカメラに抜かれるのを意識してどう倒れるかを考えていた。カメラに足向けて倒れるのはどうかとおもったけど。
なんかおしとやかキャラに変更してたなぁ
というかジャスピオンは
主人公がパンチパーマだわ
敵戦闘員のデザインが全員違うわの実験要素山盛りだったけど
次作のスピルバンは王道要素山盛りだったあたり
手応えがなかったんだろうな
シャリバン、シャイダーを幼少のみぎり熱心に見ていた世代の者です。
ジャスピオンは見た記憶が無いどころか名前すら知らなかった。ネット時代になって「ブラジルで超有名なメタルヒーロー」として知って、へー聞いたことないな。ってことは後期のメタルヒーローなのかな……(検索)……シャイダーの後なの!?ってなった。
手ごたえ無かったのは事実だと実感を持って(当時の子供視点から)言えます。
自分は特撮を見るには、もう恥ずかしい年のお兄ちゃんになっていましたが、ジャスピオンの地球に来る迄の話をお薦めします
人形アニメーション(自称アニクリエーション)の特撮時代劇、魔人ハンターミツルギ
さすがに色々斬新過すぎだった感が…
着眼点は良かったと思うけど、やはり人間態での二足のわらじは難しく1クールで突然終了してしまった
特捜ブルースワットのサブタイトル
最初「ビギニング!」→後半「ずっこけ新隊員」w
サブタイ見ただけで初期から後期への試行錯誤が良くわかりますw

Twitterでも配信しているのでフォローしていただけると嬉しいです。
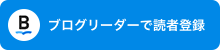

こちらのアカウントのフォロー・サイトのチェックもして頂けると嬉しいです。
https://hero-times.com/



黒って悪のイメージのある色だけど、ヒーローに取り入れたろ
という経緯で生まれたらしい、ゴーグルブラック。
バトルケニア・デンジブルーで実績のある大葉健二さんの同期である春田さんを抜擢。
結果、二年連続ブラックが加わり、両方春田さんが演じるというまさにレジェンド級の活躍